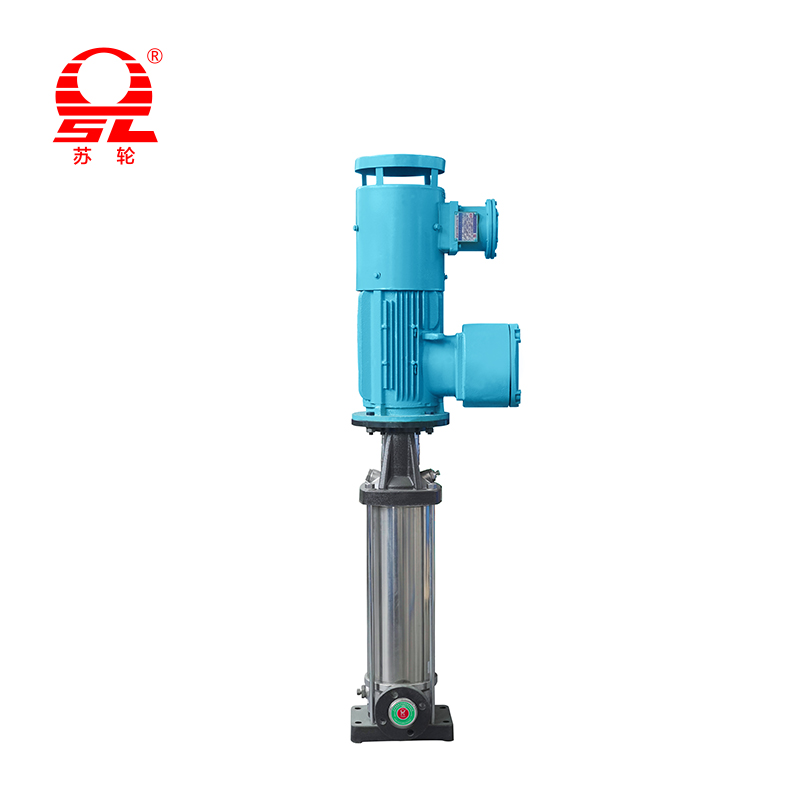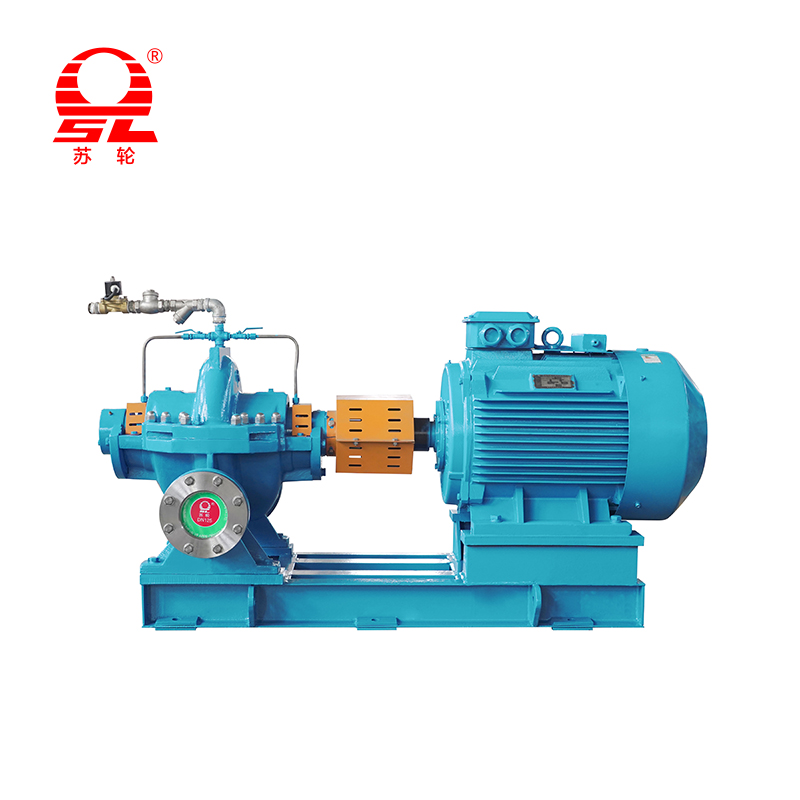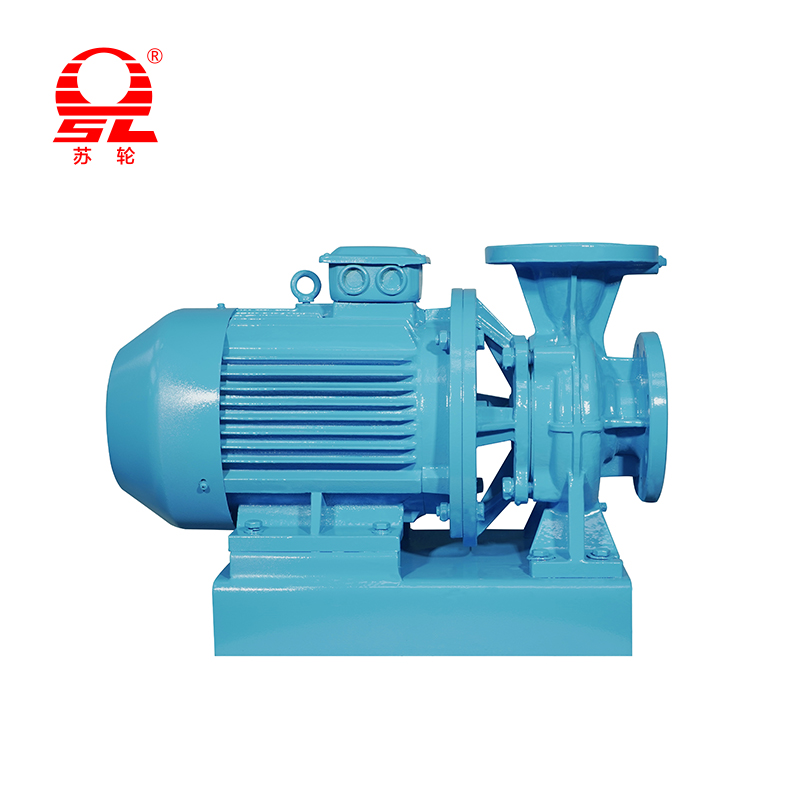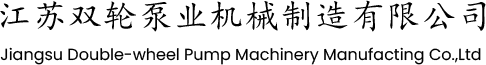自己拡大ポンプは、負圧の下で継続的に動作することができます
 2025.07.22
2025.07.22
 業界のニュース
業界のニュース
そのユニークな自己拡大機能のため、 セルフプライミングポンプ パイプラインの空気を避難させ、クイックスタートを必要とする液体輸送の機会に広く使用されています。負圧環境とは、ポンプの吸引ポート圧が大気圧よりも低い作業条件を指します。実際の産業用途では、多くの労働条件には、真空ポンプ、深い井戸水抽出、または特定の特別なプロセスリンクで一般的なネガティブ圧力環境があります。自己拡大ポンプが陰圧環境で継続的に動作できるかどうかは、設計と動作中に考慮する必要がある問題です。
セルフプライミングポンプの動作に対する陰圧環境の影響
セルフプライミングポンプのコア機能の1つは、ポンプ内の特別な構造を使用してパイプラインで空気を除去することを実現して、起動時に液体の流れを迅速に確立することです。負圧環境は、ポンプの吸引ポート圧に直接影響し、ポンプの吸引ストローク、キャビテーションの発生、シーリングシステムに大きな影響を与えます。
過度の負の圧力は、ポンプ本体の内部圧力が液体蒸気圧よりも低くなり、キャビテーションを引き起こす可能性があります。キャビテーションは、ポンプの送達効率を低下させるだけでなく、インペラやポンプケーシングなどのコンポーネントの摩耗を加速し、重度の場合は機器の損傷を引き起こします。連続的な負圧操作条件下では、ポンプシールは漏れのリスクが大きくなり、機械シールの寿命が短くなります。
ネガティブ圧力環境へのセルフプライミングポンプ設計の適応性
セルフプライミングポンプの設計には、一般に、ポンプがパイプラインから空気を除去し、吸引液の連続性を確保するために、ポンプボディの循環逆流システムが組み込まれた空気収集チャンバーまたは循環逆流システムが含まれています。一部のセルフプライミングポンプでは、特別なシールを使用し、強化ベアリングデザインを使用して、特定の範囲の負圧環境に適応します。
製造業者は通常、自己圧縮ポンプの最大許容吸引真空、つまり負の圧力制限値を提供します。この制限値は、ポンプの構造強度、シーリング材料の耐性、および液体の特性に基づいて設定されます。通常の動作中、吸引ポートの負圧はこの制限を超えることはできません。そうしないと、キャビテーションとシールの故障のリスクがあります。
負圧環境下での自己拡大ポンプの継続的な動作の制限
ほとんどのセルフプライミングポンプは、短期的または断続的な負圧条件に適しています。高い陰圧環境の下で継続的な動作には多くの制限があります。
キャビテーションのリスクの増加
負圧が大きすぎると、液体は蒸発しやすく、泡を形成します。泡はインペラの高圧領域で破裂し、インペラとポンプケーシングに衝撃を与え、損傷を与えます。
シーリングシステムの重い負担
連続的な負圧により、シーリング表面間のギャップが大きくなり、漏れのリスクが増加し、機械シールを頻繁に維持または交換する必要があります。
ポンプの吸引範囲は限られています
負圧環境は液体吸引能力を低下させ、ポンプは設計されたフローとヘッドを維持することができず、システムの安定性に影響します。
動作効率の低下
負圧操作により、エネルギー消費が増加し、ポンプの動作騒音と振動が増加し、機器の寿命が短くなります。
負圧環境に適したセルフプライミングポンプの種類
いくつかの特別に設計されたセルフプライミングポンプは、負圧環境での継続的な動作に適しています。
ガス液体混合自己供給ポンプ
液体とガス混合送達の原理を使用して、キャビテーションのリスクを減らします。これは、ガス含有量が高い労働条件に適しています。
強化された機械シールポンプ
より高い負の圧力環境に適した、シーリングの安定性を改善するために、耐摩耗性および耐腐食性のシーリング材料と構造設計を使用します。
磁気駆動自己拡大ポンプ
シャフトシールの設計、漏れポイントの減少、負の圧力の適応性の向上は、高い陰圧連続動作に適しています。
労働条件に適したポンプの種類と構成を選択することは、負圧環境での自己拡大ポンプの安全で継続的な動作を確保するための鍵です。
負圧環境での自己拡大ポンプの継続的な動作のための動作戦略
吸引圧力を厳密に制御します
キャビテーションやシールの損傷を避けるために、製造業者が指定した負圧制限よりもポンプ吸引ポート圧力が低くないことを確認してください。
パイプライン設計を最適化します
吸引パイプラインの長さと肘を減らして、過度の局所的な負圧を避け、安定した液体吸引を確保します。
定期的な検査とメンテナンスを実行します
アザラシ、ベアリング、インペラの検査を強化し、時間内に摩耗した部分を交換し、負の圧力操作によって引き起こされる障害を防ぎます。
真空保護デバイスを構成します
真空スイッチまたは圧力センサーを取り付けて、吸引ポート圧力をリアルタイムで監視し、自動的にアラームし、保護をシャットダウンします。

+86-0523- 84351 090 /+86-180 0142 8659